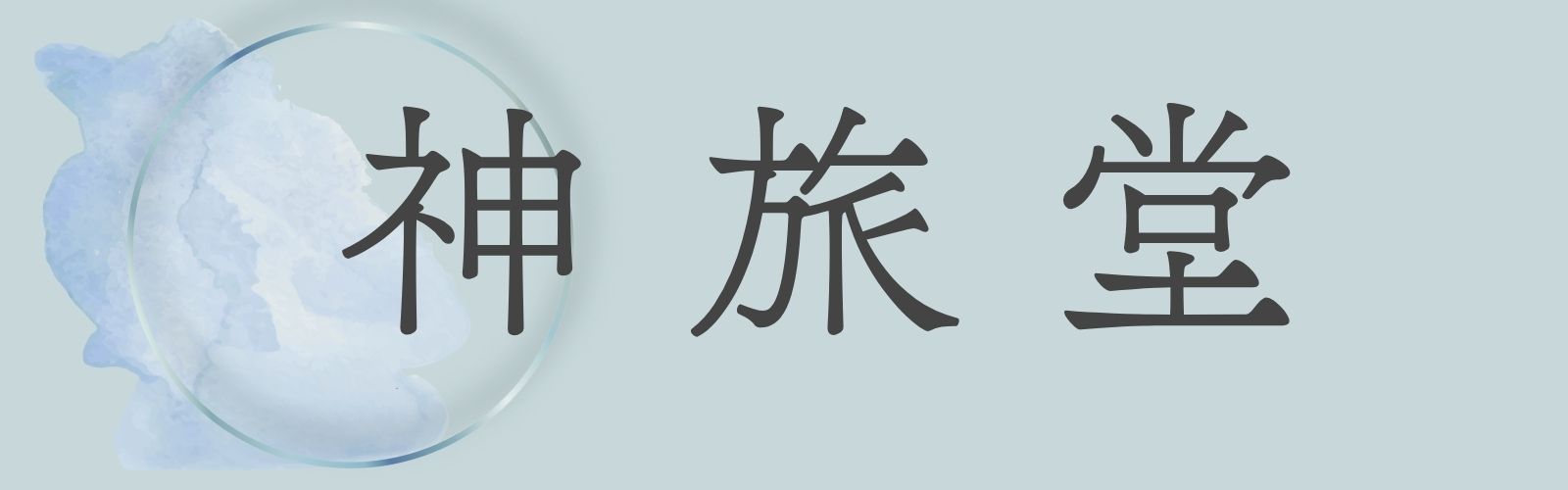ご神徳: 厄除・疫病退散・祓
主な伝承:スサノオノミコトは嵐と海を司る荒ぶる神として知られますが、その力は災いを祓う力ともされました。
平安時代の疫病流行の際には、都で行われた祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)でその御霊を鎮めたと伝えられ、これが現在の祇園祭の起こりといわれます。
人々は荒ぶる神の力を恐れつつも、その強さに「災厄を祓う守護神」としての信仰を寄せてきました。
主な鎮座地: 八坂神社(京都市)/須佐神社(島根県出雲市)
ご神徳: 厄除・祓・再生
主な伝承:黄泉の国から戻った伊邪那岐命は、自らの穢れを清めるために、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊を行いました。
そのとき、水に身をひたして体を清めるたびに多くの神々が生まれたと伝えられています。
中でも祓戸大神(ハラエドノオオカミ)や住吉三神(スミヨシサンシン)は、後に「祓いや浄化を司る神」とされ、日本の厄除け信仰の起源となりました。
主な鎮座地:阿波岐原神社(宮崎県宮崎市)/伊邪那岐神宮(兵庫県淡路市)
ご神徳: ご神徳:大祓・厄除・清め
主な伝承:祓戸大神とは、祓の儀式で唱えられる「大祓詞(おおはらえのことば)」に登場する四柱の神々の総称です。
それぞれの神は、罪や穢れを取り除き、心身を清らかに保つ役割を担っています。
・瀬織津比売神(セオリツヒメノカミ) ・速開都比売神(ハヤアキツヒメノカミ)
・気吹戸主神(イブキドヌシノカミ) ・速佐須良比売神(ハヤサスラヒメノカミ)
これらの神々は、川や風、息、流れといった自然の力を通じて、人々の穢れを祓い清める神として古くから信仰されています。
主な鎮座地:下鴨神社・祓社(京都市)/大神神社・祓戸神社(奈良県桜井市)
ご神徳: 祓・厄除・航海安全
主な伝承:イザナギノミコトの禊の際に生まれた神々のうち、住吉三神は清めと航海の守護神として知られます。
古くから海上安全の祈りとともに、心身の穢れを祓う神としても信仰されてきました。
大阪の住吉大社では、新年や節分の厄除け祈願が盛んに行われ、多くの人が「清めの力」にあやかろうと訪れます。
主な鎮座地:住吉大社(大阪市)/住吉神社(福岡市)
ご神徳: 厄除開運・国家鎮護・必勝
主な伝承:八幡大神は第十五代オウジンテンノウの御神霊とされ、古くから国を護る守護神として崇敬されました。
朝廷や武家からの信仰が厚く、石清水八幡宮では新春に「厄除大祭」が行われ、全国から多くの参拝者が訪れます。
その信仰は「戦に勝つ」だけでなく、「人生の試練に打ち勝つ」祈りにもつながっています。
主な鎮座地:石清水八幡宮(京都府八幡市)/宇佐神宮(大分県宇佐市)
ご神徳: 道開き・方除・厄除
主な伝承:天照大神の孫・瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が天から地上に降りる際、その道案内をしたと伝えられます。
サルタヒコノカミは進むべき道を示し、方位の災いを除く神として信仰されてきました。
人生の岐路に立つ人々や新しい事を始める人々が、「悪い方角を祓い、良き道をひらく神」として祈りを捧げます。
主な鎮座地:椿大神社(三重県鈴鹿市)/猿田彦神社(三重県伊勢市)