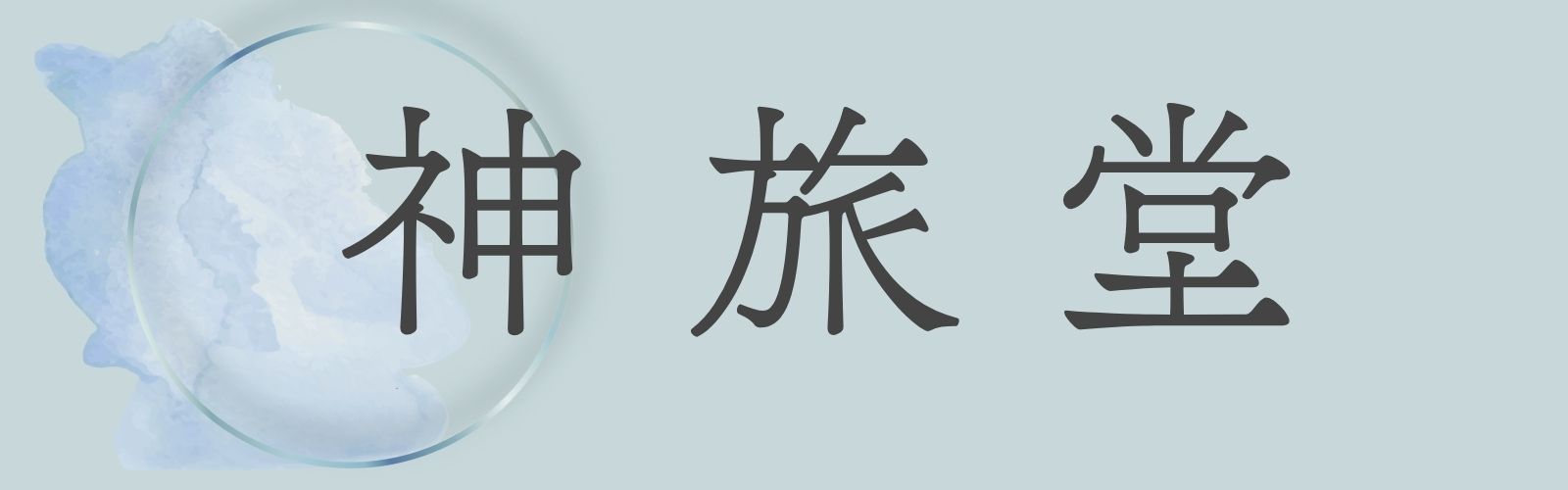この物語は、伊邪那岐命(イザナギノミコト)が火の神を生んで亡くなった妻・伊邪那美命(イザナミノミコト)を追って
黄泉の国へ行ったあと、身に付いた穢れを祓うために禊(ミソギ)を行ったことから始まります。
荒ぶる神 須佐之男命の誕生
黄泉の国から戻ったイザナギは、「私は穢れた国へ行ってしまった。身を清めねばならない」と言い、
日向の阿波岐原(アワギハラ)で禊をしました。
道具や衣を洗い流すたびに新しい神々が生まれ、最後に顔を洗い清めたとき、最も尊い三柱の神が誕生しました。
左の目から天照大御神(アマテラスオオミカミ)、
右の目から月読命(ツクヨミノミコト)、
鼻から建速須佐之男命(タケハヤスサノオオノミコト)が生まれたのです。
イザナギは「これまで多くの子を得たが、この三柱はとくに尊い」と喜び、
それぞれに世界を治める役目を与えました。
アマテラスには「高天原(たかまがはら)」を、月読命には「夜の食国(よるのおすくに)」を、
スサノオには「海原(うなばら)」を治めよと命じました。
しかし、スサノオは父の命に従わず、泣きわめいて海を治めようとしませんでした。
その泣き声は山を枯らし、川や海を干上がらせるほどで、世に災いをもたらしました。
イザナギが理由を問うと、スサノオは「母の国である根の堅洲国(ねのかたすくに)へ行きたい」と答えました。
これを聞いたイザナギは激しく怒り、「ならばこの国にはもう住むな」と言い、高天原から追放しました。
天照大御神との誓約
高天原を追放されたスサノオは、根の堅洲国へ行く前に姉のアマテラスに別れの挨拶をしようと考え、
高天原へ向かいました。
スサノオが天へ昇ると、山も川も大地も激しく揺れ動きました。
これを見たアマテラスは、「弟が高天原を奪いに来たのではないか」と疑い、男装して完全武装しました。
まず、御髪を解き、男性の髪型であるみづらに結い直し、
左右のみづらや両の手には、八尺の勾玉を緒で貫いた玉飾りを何重にも巻きつけ、
背には千入(ちのり)の靫(多くの矢を入れた入れ物)を背負い、胸には同じ千入の靫を覆う鎧を身に着けました。
そして、厳々しい弓を手にし、その弓の端を堅い地面に立てて、雪を蹴散らすような勢いで構え、スサノオを迎え撃ちました。
問い詰められたスサノオは、「邪な心はありません。ただ、姉上に別れを告げに参っただけです」と答えます。
しかしアマテラスは信じず、スサノオは潔白を証明するために「誓約(うけい)」を行うことを提案しました。
二柱は互いの持ち物を交換し、それを噛み砕いて息を吹き出しました。
アマテラスがスサノオの十拳剣(とつかのつるぎ)を天の真名井の清水で清めて噛むと、
息から三柱の女神(宗像三女神)が生まれました。
一方、スサノオがアマテラスの勾玉を清めて噛むと、五柱の男神が生まれました。
スサノオは、自分の剣から清らかな女神が生まれたのは心が潔白であった証だとして、
「誓約に勝った」と宣言しました。
これにより、高天原にとどまることを許されます。
天岩戸伝説
誓約によって潔白を示し高天原に留まることを許されたものの、 スサノオの心はなお静まらず、
やがて高天原で荒ぶる行いを見せることとなりました。
スサノオはアマテラスが耕していた田の畦(あぜ)を壊し、溝を埋め、宮殿を汚しました。
それでもアマテラスは、「酔って吐いたものだろう」「溝を壊したのは土地を惜しんだのだろう」と、
弟をかばって見逃しました。
けれども、スサノオが神聖な機屋(はたや)の屋根に穴を開け、生きたまま皮を剥いだ馬を投げ入れたとき、
そばにいた織女(おりめ)が命を落としてしまいました。
この出来事が、アマテラスが天岩戸(あまのいわと)に籠もるきっかけとなりました。
太陽の神が姿を隠したことで、高天原も地上の葦原中国(あしはらのなかつくに)も闇に包まれ、
昼と夜の区別がなくなりました。
世は常闇(とこやみ)となり、災いと悪神の声が満ちていきました。
困り果てた八百万(ヤオヨロズ)の神々は、天の安河原(あまのやすかわら)に集まり、
思金神(オモイノカネノカミ)を中心に相談を重ねました。
常世の長鳴鳥(ながなきどり)を鳴かせ、玉祖命(タマノオヤノミコト)に八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を、
伊斯許理度売命(イシコリドメノミコト)に八咫鏡(やたのかがみ)を作らせます。
そして天香具山(あまのかぐやま)の榊の枝に玉と鏡、白布と青布を掛け、祭壇を整えました。
芸能の神・天宇受売命(アメノウズメノミコト)は岩戸の前で桶を伏せて立ち、
胸をあらわにし衣の紐をゆるめ、陽気に舞い踊りました。
その滑稽な舞に八百万の神々は大笑いしました。
岩戸の中にいたアマテラスは、世が闇になったはずなのに神々の笑い声が響くことを不思議に思い、
岩戸を少し開けて様子をうかがいました。
アメノウズメが「あなた様より尊い神が現れたのです」と答え、
天児屋命(アメノコヤネノミコト)と布刀玉命(フトダマノミコト)が鏡を差し出します。
アマテラスは鏡に映る自分の姿をその新しい神と思い、さらに岩戸を開けました。
その瞬間、隠れていた天手力男神(アマノタヂカラオノカミ)がその手を取り、
岩戸の外へと引き出しました。
再び光が戻り、世界は明るさを取り戻します。
フトダマノミコトは二度とアマテラスが籠もらぬようにと、
注連縄(しめなわ)を岩戸の入り口に張り巡らせました。
そして、この騒動の原因をつくった須佐之男命は、八百万の神々の裁きによって多くの賠償を命じられ、
髭を切られ、手足の爪を抜かれ、ついに高天原から永久に追放されました。
須佐之男命と大気津比売神
地上に降りたスサノオは、お腹を空かせて食べ物を探しました。
そこで出会ったのが、食べ物をつかさどる神・大気津比売神(オオゲツヒメノカミ)です。
スサノオが食事を求めると、オオゲツヒメは鼻や口、
そして尻からさまざまな食べ物を取り出し、それを料理して差し出しました。
しかしそのようすを見たスサノオは、「汚れたものを食べさせようとしているのか」と怒り、
オオゲツヒメを斬ってしまいました。
すると、彼女の亡骸からは蚕や稲、粟、小豆、麦、大豆といった作物が生まれたのです。
その後、これらの種を生成を司る神である神産巣日神(カミムスヒノカミ)が集め、
五穀の種として地上に広めたと伝えられています。
八岐大蛇伝説
スサノオは、高天原(たかまがはら)を追われたあと、出雲の国、
肥河(ひいかわ/現在の斐伊川)の上流にある鳥髪(とりかみ)の地へ降り立ちました。
そこで、川を流れてくる箸を見つけ、人が住んでいると考えて川をさかのぼると、
一人の娘を囲んで泣いている老夫婦に出会いました。
スサノオが名をたずねると、老夫婦は国つ神の足名椎命(アシナヅチ)と手名椎命(テナヅチ)で、
娘は櫛名田比売(クシナダヒメ)と名乗りました。
老夫婦が泣いていたのは、毎年この時期になると八岐大蛇(やまたのおろち)が現れ、
八人いた娘たちが一人ずつ食べられてしまい、ついに櫛名田比売だけが残ったからだと話したのです。
老夫婦によれば、八岐大蛇は目がホオズキのように赤く、
一つの胴体に八つの頭と八つの尾を持ち、
その体は八つの谷と八つの峰を覆うほど大きく、
腹は常に血でただれて真っ赤になっているという恐ろしい姿をしていました。
スサノオは、「クシナダヒメを私の妻にくださるなら、八岐大蛇を退治しましょう」と申し出ます。
老夫婦が了承すると、スサノオはクシナダヒメの姿を櫛に変え、自分の髪に挿して守りました。
そして老夫婦に命じ、八塩折之酒(やしおおりのさけ)という強い酒を八つの大きな桶に入れ、
八つの門の前に置かせました。
やがて八岐大蛇が現れると、八つの頭をそれぞれの桶に突っ込み、
酒を飲み干して酔いつぶれ、眠ってしまいました。
スサノオはそのすきを見て十拳剣(とつかのつるぎ)を振るい、次々と頭を斬り落としました。
そして尾を斬ったとき、中から一本の立派な剣が現れます。
スサノオはこの剣を珍しいものとして姉の天照大御神(あまてらすおおみかみ)に献上しました。
これがのちに三種の神器の一つとされる天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)、
後の草薙剣(くさなぎのつるぎ)と伝えられています。

出雲の王
八岐大蛇を倒したのち、スサノオはクシナダヒメと結ばれ、安らげる地を求めて旅を続け、出雲の清らかな風の吹く地で立ち止まり、
「吾が心すがすがし」と言い宮殿を建てました。ここが須賀(すが)の地です。
そのときに「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」と詠んだ歌が、日本で最も古い和歌として伝えられています。
やがて二神の間に八島士奴美神(ヤシマジヌミノカミ)が生まれ、
さらに神大市比売(カムオオイチヒメ)を娶り、
大年神(オオトシノカミ)・宇迦之御魂神(ウカノミタマ)が生まれました。
出雲の後裔――大国主命へ
須佐之男命と奇稲田姫の系譜は、やがて大国主命(オオクニヌシノミコト)へとつながります。
八島士奴美神を祖とし、出雲一帯に広がった一族の根を示す系譜です。
若き大己貴命(オオナムチノミコト)、後の大国主命は、スサノオの住む根の国を訪れ、試練を受けました。
娘の須勢理比売命(スセリヒメノミコト)を娶るために勇気と知恵を示し、
スサノオから剣・弓矢・琴、そして「大国主命」の名を授かります。
かつて荒れ狂った神は、次の世代を導く守護者となりました。
その後、国の中心は大国主へと移り、国造りの物語が始まります。
スサノオは根の堅州国に鎮まり、祓いと豊穣を司る神として、今も崇められています。
ゆかりの神社
1. 須我神社(すがじんじゃ)
住所: 島根県雲南市
主なご利益: 縁結び・夫婦円満・災難除け
特徴: 須佐之男命と稲田比売命が新居を構えた地と伝わり、
「八雲立つ」の和歌が詠まれた場所として知られています。
境内には両神を祀る本殿のほか、縁結びのご神木「夫婦杉」や、清らかな湧水「八雲の滝」もあり、
訪れる人々の心を癒します。
2. 須佐神社(すさじんじゃ)
住所: 島根県出雲市
主なご利益: 厄除け・病気平癒・家内安全
特徴: 須佐之男命の御魂を祀る全国の総本社。出雲の深い森に包まれた荘厳な雰囲気の中に鎮座し、「日本一のスサノオの社」とも称されます。樹齢千年を超える大杉や、神聖な空気が漂う境内は、まさに神々の息づく聖地といわれています。
3. 八重垣神社(やえがきじんじゃ)
住所: 島根県松江市
主なご利益: 縁結び・夫婦和合・子宝
特徴: 須佐之男命と稲田比売命が夫婦の契りを結んだ地とされ、良縁祈願の神社として全国的に有名です。
鏡の池に紙を浮かべて占う「縁占い」が特に人気。
静かな森に囲まれた境内には、夫婦杉や稲田姫命の美しい伝承が息づいています。
4. 氷川神社(ひかわじんじゃ)
住所: 埼玉県さいたま市
主なご利益: 厄除け・縁結び・開運
特徴: 須佐之男命を主祭神とする関東屈指の古社で、全国にある氷川神社の総本社です。
2400年以上の歴史を持ち、古くから武蔵国一の宮として崇敬を集めてきました。
広大な境内と美しい参道は、四季折々の風情を楽しめる憩いの場所となっています。
5. 八坂神社(やさかじんじゃ)〔旧称:祇園社〕
住所: 京都府京都市
主なご利益: 厄除け・疫病退散・良縁成就
特徴: 牛頭天王(須佐之男命)を祀る古社で、全国の八坂神社の総本社。
祇園祭の発祥地としても名高く、夏には華やかな山鉾巡行が京都の街を彩ります。
美しく整えられた境内は、昼も夜も多くの参拝者でにぎわい、古都の中心に神の気配を感じられる場所です。